鍋の焦げ落とし素材別の注意点
鍋を浸けるお湯に「重曹」や「酢」を加えると焦げが落ちやすくなります
ただし素材によって加えるものが異なります
- ホウロウとステンレスの鍋には「重曹」
- アルミ鍋には「酢」
鍋の素材によっても扱い方が異なるので注意が必要です
【土鍋の焦げ落とし】

土鍋が熱いうちは決して水に入れないことが肝心
陶器は急激な温度変化に弱く、割れることがあるからです
焦げ付いた場合には水ではなく必ず「お湯」を入れて焦げを柔らかくします
【ホーロー鍋の焦げ落とし】

ホーロー鍋に金属タワシや硬いヘラは厳禁です
なぜなら表面のコーティングが傷ついてしまうからです
そのため焦げ付いた時でも必ず「柔らかなスポンジ」で洗います
急激な温度変化にも弱いので、熱が冷めてから「ぬるま湯」に浸けます
ぬるま湯に「重曹」を入れると焦げが柔らかくなります
それから火にかけると、より効果的です
焦げを柔らかくして、傷がつかないよう洗うのがポイント
付いてしまった傷は修復できません
【ステンレス鍋の焦げ落とし】

ステンレスはサビにくく、温度変化に強く、傷がつきにくい素材
焦げ付いた場合には金タワシなどでこすっても大丈夫です
ただし光沢は失われます
ピカピカの状態を保つなら「お湯」に浸けて焦げを柔らかくしてから
柔らかいスポンジで洗えば光沢を保てます
【鉄鍋の焦げ落とし】

鉄はサビやすい素材なので、洗剤を使わず「お湯」で洗います
焦げ付いた場合には「金タワシ」などで強くこすっても大丈夫です
洗った後に火にかけて水分を完全に飛ばし、熱いうちに油を薄く塗っておきます
もしサビがついてしまっても、スチールタワシでこすれば落ちます
お湯で洗ってから火にかけて水気を飛ばし、油を塗っておけば復活します
炒め物のような強火での調理に使うフライパン
テフロン加工の危険性が指摘されています
安全なのは「鉄製」「ステンレス製」と言われます

>安全な鉄フライパン~錆びない焦げない使い方
ステンレス製は高価ですが、錆びないことがメリットです。けれど安価な鉄製でも使い方に気を付ければ、錆びず、焦げず、長持ちします。炒め物、煮物、揚げ物、何でも使えるのが、中華料理に使われる鉄フライパン。素人が使う場合には「軽い」ことがポイントです。
コゲが落ちたら通常通りに洗います
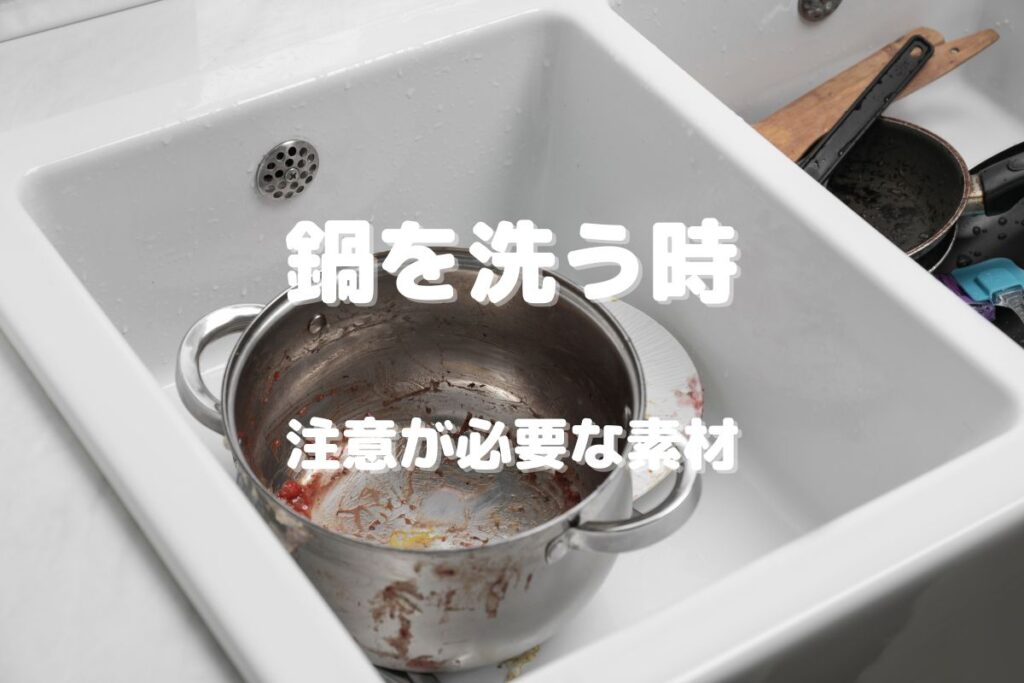
>【鍋の洗い方】土鍋・鉄鍋・アルミ鍋・ホーロー鍋を洗う
鍋の洗い方で注意することは、決して傷を付けないことです。コーティングが剥がれたまま使い続けると、有害物質が食品に混入してしまいます。例えばフッ素樹脂加工された鍋やフライパンは、特に傷が付きやすい素材です。基本的な鍋の洗い方は、どんな素材でも共通しています。