ペットと快適に暮らすうえで最も大切なことは、ちゃんと見てあげるということ
なぜなら犬猫にも個性があり、年齢や環境による変化もあるからです
例えば我が家の犬は、猫のように気まぐれで、ひとり遊びが好きでした
猫なのに、番犬のように私を見守っていた子もいます
ずうっと触れられるのが嫌いだった子が、年を取ったら一緒に寝るようになりました
長年、犬猫と暮らすうちに分かってきたことを御紹介します
言葉でのコミュニケーションができなくとも、見ていれば分かることは少なくありません
ペットにとって快適な居場所を作るための工夫

初めてペットを飼う時は、本を読むなどして情報収集をしました
ところが実際に飼ってみると違う、ということは少なくありません
例えば、ペットにとって快適な居場所を作ろうと、様々なグッズを購入します
それなのに全く使ってくれなかったりします
買い与えてみないと分からないので、使わなくても仕方がないと諦めるしかありませんが
【ペット専用スペースの確保】

家に来た最初の日には、犬も猫も室内の匂いを嗅ぎながら探検を始めます
この時には自由にさせて、全ての部屋を見せると落ち着くはずです
その後は、入ってほしくない部屋のドアを閉めておきます
専用ベッドやハウスを用意しておけば、そこを自分の居場所と感じて安心します
【ケージに慣れさせておく】

ケージのドアは開けておき、おもちゃやおやつなど置くと自分で入っていきます
すぐに出てきても構いません
ドアを閉めたり、無理に入らせたりすると、怯えてケージを嫌がるようになります
できればケージは常に出しておき、自由に出入りさせると慣れます
とはいえ病院へ連れていく場合などは、無理にでもケージに入れなければなりません
そのためケージの中は居心地よくし、優しく話しかけることも大事です
ケージに入ったことを褒めて、家に帰ったら甘やかせてあげると、あまり嫌がらなくなります
【適切な温度管理】

猫は基本的に、居心地の良い場所を自分で見つけ出します
そのため危険な場所でなければ、自由にさせてあげるのがベスト
落として割れそうな物などは、別の場所に移動させておけば安心です
真夏の暑さで、犬も猫もバテてしまうことがあります
あまり水を飲まないといわれる猫でも、大量に水を欲しがります
我が家の猫は、真夏の新潟で、犬のようにハアハア苦しそうな息をしていました
湿度が高い上に、38℃もの高温になった時です
大きなボウルに入れ、たくさん飲むと回復したようです
日向で寝ていたので、熱中症になったのかもしれません
猫は寒がりですが、チワワなど南国が原産の犬も寒がりです
冬や雨の日の散歩などには、温かな服やレインコートも必要になります
決まった場所で寝させる場合なども、断熱シートや毛布などで寒すぎない工夫が大事です
【ペットの安全に配慮する】

特に元気いっぱいの子犬や子猫の時期は、ハラハラさせられます
田舎で自由にさせていた猫は、しょっちゅう木に登って降りられなくなりました
大声で鳴く声を聞くたびに、はしごを掛けての救出です
室内飼いしていた猫は、ベランダに出て、ぴょんと手すりに飛び乗ったことがあります
マンションの10階だったので、慌てて室内へ入れました
室内飼いだからといって、安心もしていられません
犬も猫も、何でも口に入れてしまうことがあることにも注意が必要です
そのためクリップや小さな置物などは、出しっぱなしにできません
我が家の猫は、荷造り紐を飲み込んだことがあります
口から出ている紐を引っ張ったら、びっくりするほど長く出てきました
電気のコードは気を付けてカバーを付けていましたが、ビニール紐は不注意でした
観葉植物や食品にも、ペットが中毒を起こすものがあります
例えばアイビー、ポトス、モンステラ、ポインセチア、アロエ、スイセン、スズランなど
スイセンやスズランは人にとっても猛毒なので、庭などに植えないほうが安全です
スズランを入れていたコップの水を子供が飲んで、中毒を起こした事故もあるといいます
我が家の猫は、イカの刺身を盗み食いして、立てなくなりました
しばらくしたら回復しましたが、ペットに人の食べ物を与えないことも大事です
ペットの犬をしつける

犬は、リーダーが決まっていることで安心します
なぜなら集団行動をする習性があるためです
そのため飼い主がリーダー役を務めないと、犬は自分がリーダーになろうとします
しつけは、犬との信頼関係を築き、安全を確保するために非常に大切です
そして一貫性のある態度が、ペットとの信頼関係を築くポイントになります
【ドッグトレーニング】

我が家では、大型犬を飼い始めた時に初めてドッグトレーニングを受けました
パピースクールの最初は、グループレッスンです
多くの犬と一緒に訓練することで、勝手に遊んだり喧嘩したりしなくなります
とはいえ元気いっぱいの子犬にとっては、これが難しい
まずは飼い主だけに注意を向けることから訓練します
それがリードを付けて、飼い主の真横を一緒に歩く練習です
飼い主より前に出たり、遅れたりしないよう、リードを引きながら歩かせます
すると最初はキョロキョロしていた子犬でも、リードを引くと飼い主を見上げます
【しつけの基本と注意点】
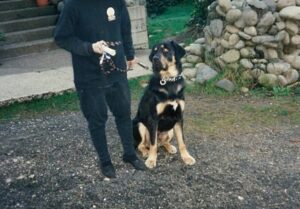
しつけで大事なのは「声」のトーンだと言われました
ビシっと大きな声でダメと言うことで、いけないことを覚えます
すると次第に飼い主の動きに注意しながら歩けるようになります
上からの大きな声を聞くだけでも、犬は十分に怖いと感じています
そのため、それ以上の恐怖を与えない配慮が必要です
叩いたりするのは最悪で、人間の手を怖がることを「ハンド・シャイ」といいます
こうなると、頭をなでられるのも、体に触れられるのも怖がるようになります
そして怯えた犬が、人を噛んだりすることもあります
人間の手は、なでたり、おやつをくれたりするもの
そんな安心感が、信頼関係の基本です
【老犬でもしつけられる】

ことわざに「老犬はしつけられない」という言葉があります
長年の習慣が身についてしまうと治らない、という場合などに使う言葉です
ですが根気よくしつければ、老犬でも悪い習慣を改められます
甘やかされてきた犬を預かった時に、それは実感したことです
その子は食卓で食べ物を分けてもらってきたため、もらえるまで吠え続けていました
我が家では人間の食べ物を絶対に与えないという方針です
そのため食事中は、ガレージにエサを置いて、締め出すことにしました
すると自分の自分のエサはあるのに、大暴れです
ドアに体当たりしたり、引っかいたり、吠えたり、走り回ったり
とはいえ危ないものは高い場所に置き、車は外に出してあるので、好きなだけ暴れさせました
そして食事が終わってから、犬用おやつを与えました
すると数日後にはガレージの中で吠えなくなり、室内においても大丈夫
テーブルの周りをウロウロはしましたが、吠えて暴れたりはしなくなりました
ペットの猫をしつける

猫は犬ほどしつけを必要としませんが、トイレの場所だけは覚えてもらわないと困ります
すぐに覚える子もいれば、なかなか覚えられない子もいます
特に野良猫だった子は、室内のトイレを使いたがらないことがあります
粗相をしてしまった場合は、その場所を綺麗に拭いた後「レモン」で拭いておくと効果的です
決して叩いたりしてはいけません
信頼関係が築けず、かえって、わざと別の場所にオシッコすることもあります
長毛種の猫は、猫砂が毛にからまるのが嫌だったようです
そのためか床に置いてある紙などにオシッコすることがありました
しばらくは、ゴミ置き場にある古新聞紙をもらってきて使っていました
けれど犬用のトイレシーツが最適で、猫も満足したようです
ウンチは水洗トイレに流し、シーツは燃やせるゴミへ出せます
【猫は室内飼いのほうが安全】

交通量の少ない田舎ではいいかもしれませんが、都会では室内飼いのほうが安心できます
田舎で自由にさせていた猫が、都会に引っ越してから車にひかれてしまいました
それ以来ずっと、猫は外に出さないと決めています
友人は、飼い始めたばかりの子猫を自分の車でひいてしまったといいます
雄猫の場合は、1か月以上も帰ってこないことがありました
そして帰ってきた時には、ノミだらけだったようです
猫が持ち込んだノミが室内で繁殖し、害虫駆除業者を呼ぶしかなくなりました
猫は高いところでも登れるし、狭い場所でも入れます
危険な場所でも飛び乗ったりするのでハラハラします
そのため外に出さないほうが安全です
室内だけで飼っていれば、外へ出たがりません
出たがるのは野良育ちの子か、最初から自由に出入りさせている場合です
【避妊手術をしてあげる】

外に出すにしろ、室内飼いにしろ、避妊手術は大切です
特に外に出している雌猫は、いつの間にか妊娠して、子猫が増えてしまうことがあります
発情期の猫は、ものすごい声で鳴き、どうすることもできません
繁殖させるのでなければ、避妊手術をしたほうが、猫にとっても楽です
子猫のうちに手術すると、ずうっと子猫の気分で育つといいます
雄猫なら雌猫をめぐって喧嘩をする危険もあります
我が家の雄猫は、傷口を縫うほどの怪我をしたこともありました
ペットの健康を維持するための食事管理

犬猫に人間の食べ物を与えるのは、健康上も良くありません
特に味付けしてあるものは塩分が多く、腎臓病などの原因となります
何でも食べさせて肥満にするのも不健康です
【ドライフード】
ドライフードのほうが、歯の健康のためにも良いと言われます
我が家では人間の食べ物を与えないことはもちろん、ずっとドライフードだけでした
柔らかなウェットフードは、食が細くなった高齢期や病気の時だけで十分だと思います
ウェットフードなどは、おやつとして、たまにあげるだけ
室内飼いしていた猫たちが19歳、22歳と長寿だったのは、食事のおかげかもしれません
猫は、満腹になったら、それ以上は食べません
そのため我が家ではドライフードを常に出してありました
ところが犬は、あるだけ全部を食べようとするので、食事の時しか出しません
食事の前には犬にお座りさせて「待て」「よし」と食事の指示を出します
すると一緒に飼っていた猫まで、指示が出るまで、お座りするようになりました
【ペットのアレルギー】

犬猫にもアレルギーを持っている場合があります
我が家の犬は原因不明の皮膚病で、動物病院ではアレルギーではないかと言われました
様々なドッグフードを試してみたものの、結局は気候のせいではないかという結論です
その子は乾燥地帯で生まれ、原産地も乾燥地帯
皮膚病が出たのは、湿気の多い土地に住んでからのことでした
環境が変わると、犬の皮膚病は治りました
そのため、高価なドッグフードが必ずしも良いわけではないことも分かりました
ペットを飼っている場合、災害時の備えも必須です

災害時には、ペットも飼い主も気が動転しています。そのため一緒に避難できない場合もあるはずです。例えば、怯えたワンちゃん、猫ちゃんが家から飛び出して行ったり。家から逃げ出すのが精いっぱいで、ペットまで連れ出せない場合だってあります。どこかで生き延びてさえいれば、必ず戻ってくるはずです。そんな時を想定した備えもあれば、非常時でも、ペットの安全を守れます。