災害時には、ペットも飼い主も気が動転しています
そのため一緒に避難できない場合もあるはずです
例えば、怯えたワンちゃん、猫ちゃんが家から飛び出して行ったり
家から逃げ出すのが精いっぱいで、ペットまで連れ出せない場合だってあります
どこかで生き延びてさえいれば、必ず戻ってくるはずです
そんな時を想定した備えもあれば、非常時でも、ペットの安全を守れます
災害時のペットの避難場所

ペットを受け入れてくれる避難場所は、あらかじめ調べておくことが大切です
なぜなら災害時には、スマホなどが使えない場合が多いからです
2024年の毎日新聞には、全国で6か所しかないと報じられています
>場所が…人手が… ペット同伴専用避難所、開設自治体6市のみ
それが福島、北九州、佐賀、長崎、熊本、宮崎の6市だそうです
【ペットの避難場所を探しておく】
ペットの避難所を探せるのが「うちトコ動物避難所マップ」というサイト
動物の種類、場所、避難所の形態で検索ができます
- 種類:小型犬(10㎏以下)中型犬(10~20㎏)大型犬(20㎏以上)猫、その他
- 場所:都道府県、市町村
- 避難所の形態:動物のみ預かる、人と動物がともに避難する、指定避難所
犬か猫か、大きさなどで、受け入れてもらえない場合も出てきます
特に大型犬を飼っている場合は、難しいはずです
その場合は、車やテントでの生活を余儀なくされるかもしれません
【ペットを連れての避難】
できるだけペットは連れて避難したいものです
自宅に戻った飼い主が、二次災害に遭う危険性もあるからです
取り残されたペットが、繁殖して増えてしまうケースもあるといいます
そのため、ペットを連れてどのように避難するか、避難経路の確認も必要です
日ごろからケージに慣れさせておかないと、すみやかに避難できません
とはいえケージに入れる余裕もない場合は、抱っこして逃げるしかありません
怯えたペットが逃げ出さないよう、体を固定できるリードなども必要です
【避難所でのペットとの生活】
避難所には、ペットの備蓄はありません
そのためフードや食器、トイレ用品などの備えは必須です
むやみに鳴いたり吠えたりすると、周囲にも、自分にもストレスです
犬の場合なら、屋外に繋いでおかなければいけない場合もあります
決められた場所で排泄する訓練をしておくことも大事です
日ごろからできる訓練ですし、しつけは日常生活でも役立ちます
【災害時のペット用必需品リスト】
- 食糧と水:ペットが数日間生き延びるために十分な量の食糧と水
- 食器:軽くて持ち運べる折りたたみ食器が便利
- おもちゃや毛布:ペットが安心できる、使い慣れたおもちゃや毛布
- 予備のリードや首輪:避難場所での安全確保のため
- ペット用トイレ用品:持ち運べる軽い猫砂やペットシーツ、ビニール袋など
- 薬:持病があるペットの薬、応急処置キット
ペットが興奮している場合に備えて、睡眠剤を用意しておくことも一案です
これはアメリカから日本へ、猫を連れてくる時、動物病院ですすめられました
当時は、料金を払えば、手荷物として客席にケージを持ちこむことが可能でした
災害時にペットとはぐれてしまった場合

ペットを連れて避難できなかった場合に備える必要もあります
災害時には、とにかく自分の身の安全が第一
そのためペットを連れて避難できないことも考えられます
まずは、すぐにペットを見つけられるよう、首輪に名札を付けておくことが大事です
動物病院などで、マイクロチップを装着できる場合もあります
はぐれてしまったペットを探す場合に役立つのが、ペットの写真
それをプリントできる防災バッグがあります

ペットの写真をプリントしたトートバッグは、普段使いもできます
シンプルで可愛いデザインなので、目につく場所に置いても違和感がありません
ここに自分用とペット用の防災グッズを入れておいてもOK
スマホが使えない場合でも、写真付きバッグで探せるのは、とっても便利
防災グッズ10点セットのほか、バッグ単品でも購入できます
水や食料といった備蓄にばかり目が向きがちですが、それは避難できた後のこと
まずは逃げるための対策が大事です
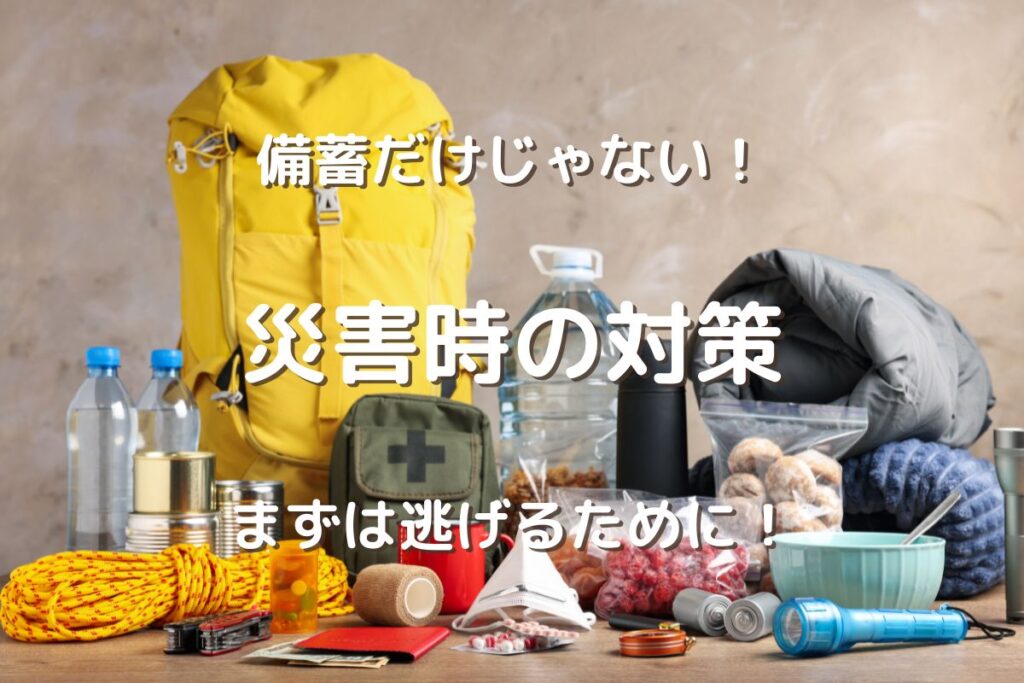
防災は、いつか必ず起こることを前提として備えることが大事です。いつ事故や災害が発生するかは、誰にも分かりません。避けられない自然災害に備えてできることは、逃げることだけかもしれません。そのため、逃げるための備えと知識が大切。